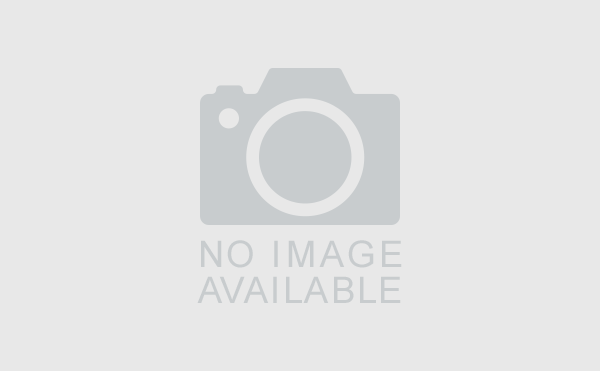DS検定:リテラシーレベルの資格について
初めまして、昨年12月からベルーフのメンバーに加入させて頂きましたS.Kです。
研修生ブログの管理人の方より、「取得した資格(DS検定 リテラシーレベル)」に関するお話を聞きたいという事で、
DS検定の受験体験記などを書かせて頂きます。
宜しくお願い致します。
※以降ではデータサイエンティストの表記が2つございます。DSはデータサイエンスの略称としても使用される為、
検定名のデータサイエンティストはDS、専門職としてのデータサイエンティストはDSciとしています。
始めに、DS(データサイエンティスト)検定(現在はリテラシーレベルのみ)は、一般社団法人データサイエンティスト協会が実施している検定で、
DSciを目指す方の知識の体系的整理や心構えの会得に資する検定といえると思います。
一方で、DS検定を取得しなくてもDSciにはなる事は可能ですので、自分である程度道筋をつけていく自信のある方には積極的にはお勧めしません。
DSciはデータの収集から前処理、統計的分析など求められるスキルの裾野が広く、
自分の現在の知識レベルの確認と今後どの様な事項の研鑽が必要かのあたりをつける上で、DS検定を受験して良かったと個人的には思いました。
ただ、リテラシーレベルでは実務で通用するレベルではありませんので、実際のデータ分析を積む過程で不足している事項を確認し、
主体的に補完していく姿勢が必要だと分析を進めていく過程で感じました。
実際にデータを活用する上では、使用許諾の問題から、リサーチデザイン、サンプルサイズの設計に至るまで、
事前の準備をしっかり行う事の重要性を痛感する機会も少なくありませんでした。
分析の途上で、分析だけでなく前処理や後処理まで、しっかり気を配って準備していく事の大事さを思い知ると共に、
DSciを目指す上で総合力と深い専門性の両立が求められる事を再認識致しました。
さて、DSciには大きく3系統のスキルセットが必要といわれています(https://parallelcareerlab.com/?p=1663)。
・ビジネス力:課題背景を理解し、「ビジネス課題を整理・解決に導く」力
・データサイエンス力:情報処理、人工知能、統計学などの「情報科学系の知恵を理解し活用する」力
・データエンジニアリング力:データサイエンスを意味のある形として、「実装・運用出来る(プログラミング)」力
DS検定は、データの前処理など統計検定のスコープにはない事項も網羅していますので、補完的に活用の余地があると感じました。
また、どこかのワークショップでの話では、ビジネス力は実務経験による所が大きいとありましたので、
データサイエンス力ないしデータエンジニアリング力のリテラシーをつける所から入る方が多いのではないかという印象です。
※ビジネス力から始めてもやりようによっては自力である程度のレベルに到達可能だとは思いますが、初学者にはあまりお勧め出来ません。
あえて申し上げるまでもないのかもしれませんが、僭越ながら自分の主戦場をどのスキルセットにするのかを事前によく吟味の上、
研鑽を積んでいくとより良い結果につながる確率が高まりそうだという事を強調しておきます。
そうする事で、自分の特徴はこれというのを採用担当の方にしっかり打ち出せる様になりますので、キャリアアップを図る上でも有益かと思います。
私の場合には、データサイエンス力に力を入れたいと考えていましたので、統計検定2級の取得に向けて勉強をしつつ、
日々のポートフォリオの作成を通じて不足事項の自己学習を進めています。
研修では、講師が自分に何をしてくれるかではなく、自分が主体的に何が出来るかを念頭に置いて訓練に勤しんでいます。
ベルーフでは就労に向けてポートフォリオを作成する機会もありますが、実際に実務経験を積む事を企図している「IT実務演習」や「ITプロジェクト」
を通じて、実際の失敗/成功体験を積む過程で多くを学ぶ事が出来るのは、ベルーフの他にはない強みといえるのではないかと感じております。
ベルーフは、プログラミング等のテクノロジー系研修に加えて、ビジネス系研修にも注力しているだけではなく、
自主自立を重んじる環境でスタッフの方が伴走して下さるので、やりたい事が明確になっている方にはおススメの事業所です。
なお、例年8月には成果発表や政策提言等の企画を研修生が主体となって行う「総合説明会」を開催しておりますので、
興味を持たれた方は是非来年度の総合説明会を視聴して頂けると、施設長の吉崎が喜ぶと思いますので宜しくお願い申し上げます(笑)
今回の記事はここまでになります。
次回の研修生ブログまでには受験出来そうかと思いますので、次回は「統計検定」に関する記事を書こうと企図しております。
あくまで予定ですので変更になってしまう可能性はございます事、ご了承下さい。
本記事を閲覧された方々におかれましては、お忙しいにもかかわらずここまでご覧頂きありがとうございました。
今回の記事が、DS検定の位置付けや活用法を知りたい方、研修生の研修内容に興味のある企業の方、
並びにベルーフの利用を検討されている方々にとりまして、少しでも参考になっていれば幸いです。